後編「雇用後」従業員を雇ったらおさえておきたい人事・労務業務
目次
従業員を雇ったら労務関係の資料を整える
この業務は雇用主としての大切な義務にもなりますので、必ずおさえておきましょう。

- 労働条件の通知
従業員・スタッフの採用が決定したら、会社は従業員一人一人の労働条件を書面によって明示しなければなりません。一般的には「労働条件通知書」を作成し、アルバイト・パートに関わらず全ての従業員に交付します。また、従業員の合意確認のために「雇用契約書」も併せて準備し、署名・押印をもらうことが望ましいでしょう。
- 社会保険・労働保険の加入手続き
社会保険(健康保険、年金保険、介護保険)と、労働保険(労災保険、雇用保険)は、国の社会保険制度です。そして、雇用主となると、従業員・スタッフのために加入の手続きが必要となります。それぞれの保険について、加入の対象となる従業員や手続きの届け先などが異なる為、注意が必要です。また、届出の期日などもありますので、遅れの無いよう手続き注意しましょう。
詳しくはこちらのコラムも、会社設立・雇用したら「労働保険・社会保険の手続き」≫
- 労務管理書類(法定三帳簿)を作成・保管
労働者を雇用したら必要となる労務管理の資料として、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3があります。この3つは、従業員を雇った際に必ず作成し管理することが労働基準法によって定められており、「法定三帳簿」とも呼ばれます。
- トラブルを避けるための書類の作成
法律で求められている書類とは他に、おさえていただきたいものが「トラブルを避けるための書類」を準備することです。従業員による情報漏洩や重大な過失など、様々な起こりうるトラブルがあります。そのようなトラブルを避けるために適切な契約書や誓約書、確認書類を整えましょう。
詳しくは、「トラブルを避けるために準備すべき書類(近日公開)」≫のコラムでも紹介していますので、ご参考にしてください。
労働保険・社会保険関係の書類を会社に代わって作成・提出もしております。
人材を育てる(研修・キャリアアップサポート)
経営者の方にとって、事業を支えてくれる従業員を育てることは大切なことです。せっかく雇った従業員・スタッフも、日々の業務を与え、作業させているだけでは成長は望めません。
それぞれの従業員・スタッフが自分自身で考え日々の職務を行ってもらえるよう、学びや気づきの機会を与えることが従業員を育てるためには欠かせません。そして、その学び・気づきの機会となるのが研修です。
ビジネスマナー研修、コミュニケーション研修、接遇・ホスピタリティ研修、リーダーシップ研修などビジネスをする上で必要となるスキルを身に着ける研修もあれば、ハラスメントや情報漏洩など職場で起こりうるトラブルへの意識付けをするための研修もあります。それぞれの事業の内容や、職場のニーズに合わせたものを選び、実施することで、従業員・スタッフの成長につながるだけでなく、事業にとってもプラスになってくれるでしょう。
厚生労働省の「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する報告書」によると、「人材育成」に取り組むことで「従業員の働く意欲の向上」に効果があることも報告されています。そのほかにも、「研修制度がある職場」は求人募集をする際に大きなアピールポイントとにもなります。
「自社に合った研修が分からない」など、職場での研修についてお悩みの方は、ご相談ください。

従業員を定着させるための環境整備(ライフイベントにあわせた働き方のサポート)

大切な従業員が継続して働くために重要なことは、それぞれの従業員が「働きやすい」と感じる職場であることです。
厚生労働省の「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する報告書」によると、「働きがい」とあわせて「働きやすい職場」であることは、
以下の3つの効果があるとされています。
- 従業員の仕事に対する意欲が高まる
- 従業員が定着する
- 会社の業績が上がる
「働きやすい職場」であることの重要な条件として挙げられるのが、それぞれの従業員のライフイベントに応じた職場環境が整っているかです。
誰もが、結婚、出産・育児、介護、入院など、様々なライフイベントを迎える可能性があります。
従業員がこのようライフイベントを迎えた時に、職場が事情を理解し、その従業員が継続して働ける環境があることが重要です。特に近年は「働き方改革」のような政府の政策などもあり、「働きやすい職場」であることが重要視されています。
従業員のライフイベントに対応した職場環境を整えるために、おさえていただきたいものは以下の通りです。
これらの対応が職場でできるように整えておきましょう。
産休とは、産前(出産予定日の6週間前、双子以上は14週間前から)と産後(出産翌日から8週間)を指します。産前休業は希望者のみですが、産後休業は法律上必ず休まなければならないとされています。(医師が就労可能と認めた場合、本人の希望により産後6週間を経過後に就業可能です)
従業員の産休・出産にあたっては、以下の手続きが必要となります(社会保険加入者の場合)
- 社会保険料の免除手続き
- 出産手当金の申請
なお、2022年10月より、男性(配偶者)も出生後の産休(※)取得が認められることになりました。(※出生時育児休業)
産後休業終了日の翌日から子供の1歳の誕生日までが育児休業の取得期間となります。(ただし、保育所に入所を希望しているが入所できない場合などの事情がある際は最大2歳まで取得が可能です。)
育児休業については、女性・男性(配偶者)ともに取得が可能です。
従業員の育児休業にあたっては、以下の手続きが必要となります。
①社会保険の免除手続き(社会保険加入者)
②育児休業給付金の申請(雇用保険加入者)
従業員が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休業です。
付与日数については「育児介護休業法」で定められていますが、最低条件である為、法定以上の休業を希望する場合の対応も決めておきましょう。雇用保険加入者は休業中に介護休業給付金を受給できるので、要件に合う従業員の場合は受給のための手続きを行ってください。
参考:介護休業制度|厚生労働省
傷病による休職制度とは、ケガや病気などで長期間就業が不可能となった場合に一定期間休職できる制度です。育児や介護休業と異なり「法定の休業」にはならず会社の任意の制度です。そのため、傷病による休職制度を設けるためには、休職期間や復職の要件などあらかじめ就業規則に規定をしておく必要があります。
また、休職期間中、社会保険加入者であれば「傷病手当金」を受けることができます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
育児や介護、通院など、様々な事情で既定の勤務時間での勤務が難しくなることもあります。そのような事情に対応できるように、短時間労働やフレックスタイム制などの導入をされる職場も年々増えてきています。
このような、働き方制度を導入するには、あらかじめ就業規則を整えておくことがポイントとなります。
最近では、新型コロナウィルス感染症により、感染したり濃厚接触者になったりする従業員が非常に増え、どのような対応を取ったらいいのかのご相談が多くなっています。
また、台風などの警報発令時や予期せぬ災害発生時の対応について、予め想定できる緊急時の対応は事前に社内で決めておくことをおすすめします。
(新型コロナウィルス感染症による感染者・濃厚接触者、またワクチンの接種後の休暇の取扱いや、職場での対応については当事務所までご相談ください。)
上記にあげた中でも、産休・育児休業、介護休業の取得については、国が定めている義務ですので、以下を参考に職場での対応・規定を整えておきましょう。
また、2022年4月から義務化される「改正育児・介護休業法」により、職場環境の整備や就業規則への変更などの対応が必要となりますので漏れなく対応しましょう。
参考:
また、「働きやすい職場」においては、「職場のコンプライアンス」も重要となります。職場の労務環境がしっかりと整っているかもしっかり確認しましょう。
「労務環境チェック」について詳しくはこちら≫
従業員の退職の対応
従業員・スタッフも、いつしか退職する日がやってきます。その際にも重要な手続きなどの対応が必要となります。
経営者の方が従業員の退職の際におさえていただきたい労務業務は以下の通りになります。
- 退職届の受理
- 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
- 社会保険料の控除
- 住民税の手続き(「給与所得者異動届」の提出)
- 源泉徴収票の発行
- 離職票・退職証明書の発行(※退職者の希望に応じて)
- 退職時の誓約書
- 退職金の支払いと控除計算(※ある場合)
退職時の手続きは、退職後の従業員の生活にも大きくかかわることですので、漏れや遅れが無いように注意しましょう。また、退職後に情報漏洩などのトラブルが発生しないため、誓約書などを交わしておくことも大切です。

まとめ
従業員を雇用する経営者の方にとって、「人事」「労務」は本業と同様に大切な業務です。適切な従業員を採用し、従業員にとって働く意欲を高めるための環境を整え、そして会社の業績に繋げるには欠かせない業務とも言えます。
大・中規模の企業であれば、このような「人事」・「労務」業務は人事部や総務部などの専門部門が担い任せておけるのですが、小規模の事業所やクリニックではなかなかそのようにはいかないのが現実です。
本業に専念したい、人事・労務に関する業務を効率的・効果的に行いたい、とお考えのクリニック・中小企業の経営者の方は、当事業所にご相談ください。従業員の採用、雇用、退職に必要な手続き、労務環境チェックなど、労務に関するサポートを行っております。
従業員の採用から退職に関するご相談以外にも、社会保険・労働保険に関する手続きのサポート、研修実施や助成金についてのご相談など、リーズナブルな価格で対応しております。
お客様の目線になり親身になること、そして経営者と従業員のみなさまがともに成長できることをモットーにアドバイスさせていただいております。
*** 社労士業務・サービス***
- まずは「労務環境チェック」
- 従業員を雇ったらおさえておきたい人事・労務業務
「雇用前」前編 「雇用後」後編 - 会社設立・雇用したら「労働保険・社会保険の手続き」
- 雇用契約の時などに「人事・労務各種書類の作成・提供」
- 会社のルールを整備するなら「就業規則・諸規定の作成・見直し」
- 残業時間が気になったら「労働時間管理」
- 給与を見直すなら「給与計算」
- 使える助成金を知りたいときは「助成金の提案・申請」
- 従業員の能力を高めたいなら「社員研修」
- できていますか?職場の「メンタルヘルス対策」
- 会社を守る「労働問題対応」前編
会社を守る「労働問題対応」後編
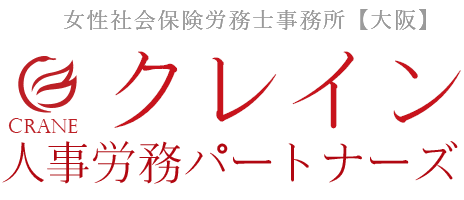






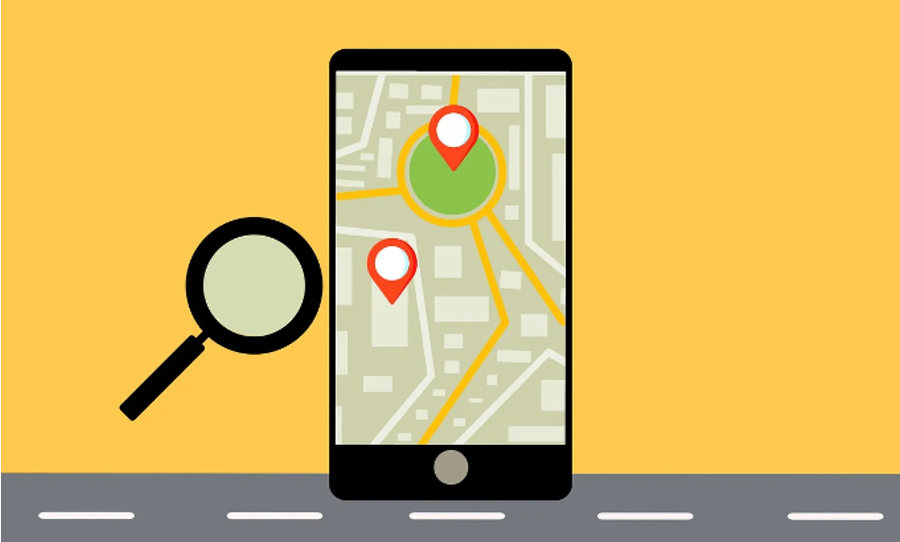
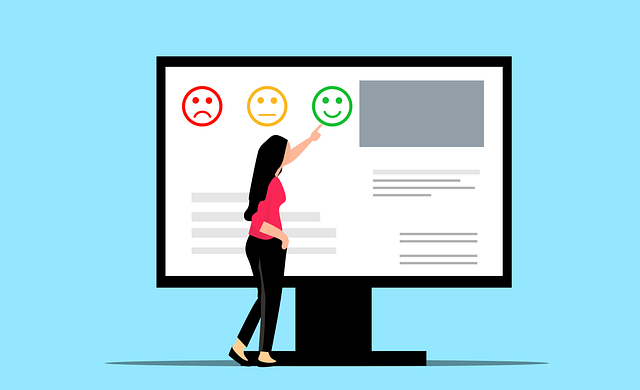


 無料相談・お問い合せ
無料相談・お問い合せ 072-965-7771
072-965-7771